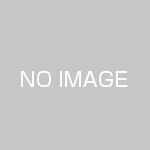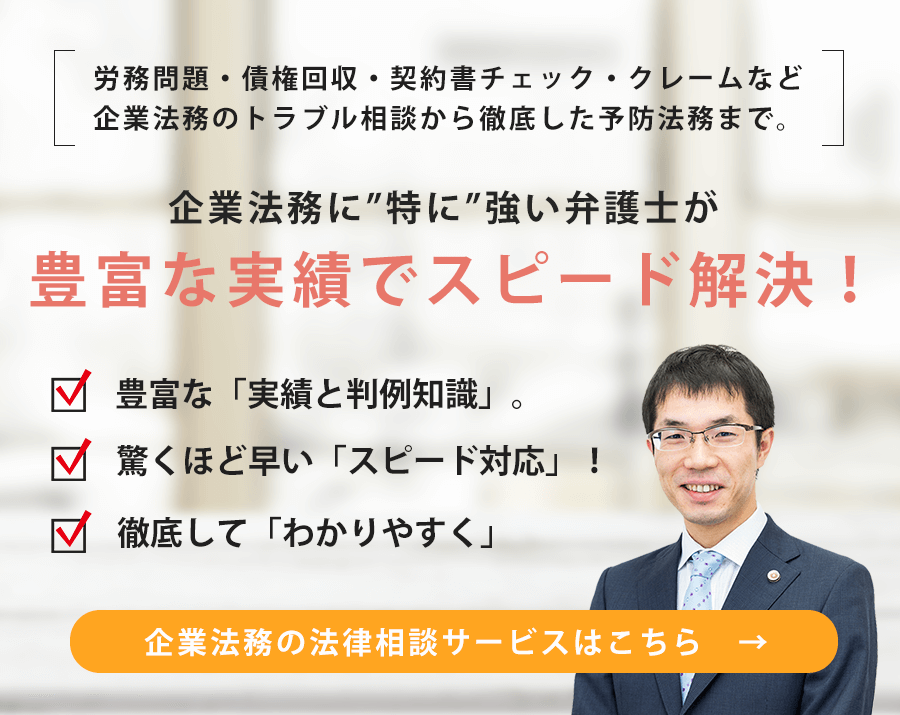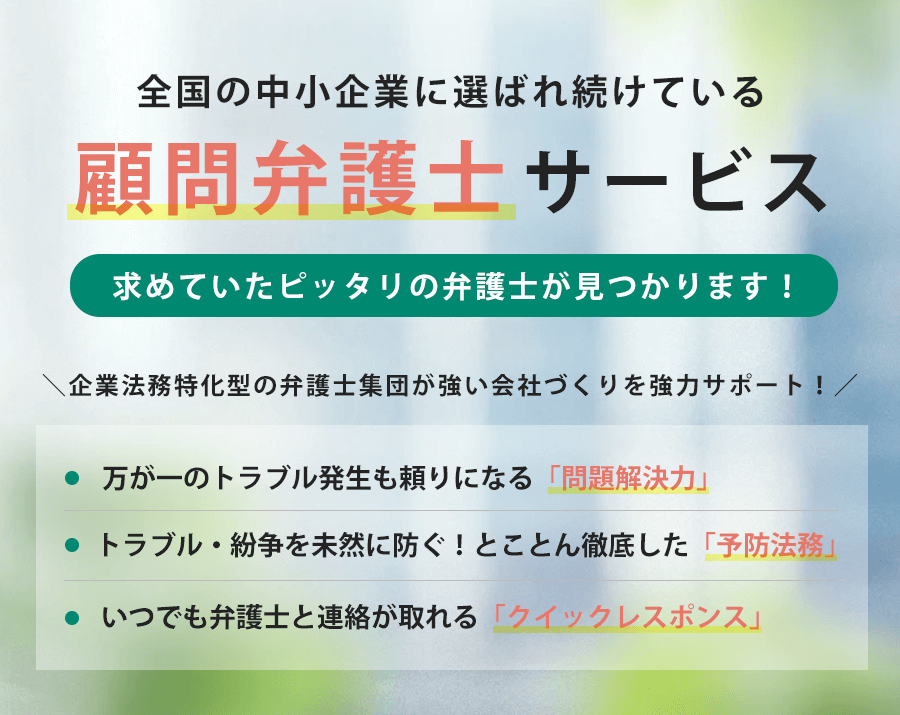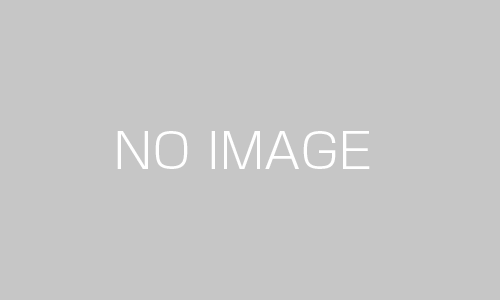東京地裁R6.12.19
廃棄物収集・運搬等の業務に従事していた従業員が、1日あたり30分の休憩しかとれていなかったなどと主張して、割増賃金を請求
→雇用契約においては、1勤務日当たりの2時間の休憩時間を与えることが契約内容になっていた。就業規則でも2時間を休憩時間とすることが定められ、会社は従業員らに2時間程度の休憩を取るように指導していたことが認められることからすると、会社において、2時間の休憩時間を従業員の権利として与えていたものと認められる。そうであるにもかかわらず休憩時間がなかったというためには、単に当該労働者が休憩を取らずに業務に従事していたという事実のみでは足りず、休憩時間を取らずに業務をせざるを得ないほどの業務量や勤務形態であったなど、休憩を取らずに間断なく労務の提供をすべきことを使用者から明示又は黙示に義務付けられていたと評価できる場合でなければならない。
本件では1勤務日当たり2時間の休憩をいつどのようにとるかは各従業員に委ねられており、路上やコンビニエンスストア等の駐車場に塵芥車を止めて車内又は車外で適宜休憩を取ることが可能な状況であったといえる。30分を超えて休憩時間を取ることができなかったとは認められず、会社の主張通り、2時間の休憩をとっていたと認めるのが相当であると判断
休憩が取れていなかったという労働者の主張について、会社側に有利な判断が示されました。
残業代請求訴訟の中で、「就業規則通り休憩が取れていなかったからその時間も賃金を払え」という主張が労働者からされることは多いです。
特に2時間、3時間といった通常より長い休憩が定められている場合は、そのような主張が出て来やすいように思います。
ポストの裁判例は、この論点について、 「休憩を取らずに間断なく労務の提供をすべきことを使用者から明示又は黙示に義務付けられていたと評価できる場合でなければならない」 という、使用者側に有利とも思える基準で判断しており、注目されます。 割増賃金請求事件で、使用者側の反論の際に使えそうな裁判例です。
ただ、本件は、社外で勤務する運転手であり、自分の判断で休憩がとれる立場にあった反面、使用者から見ればいつ休憩をとっているかを把握しづらかったと思われます。 そのような本件の事情も影響しているように思われます。
休憩時間に関するルールは以下でも解説しています。あわせてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/3553.html