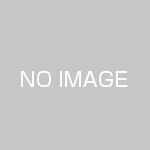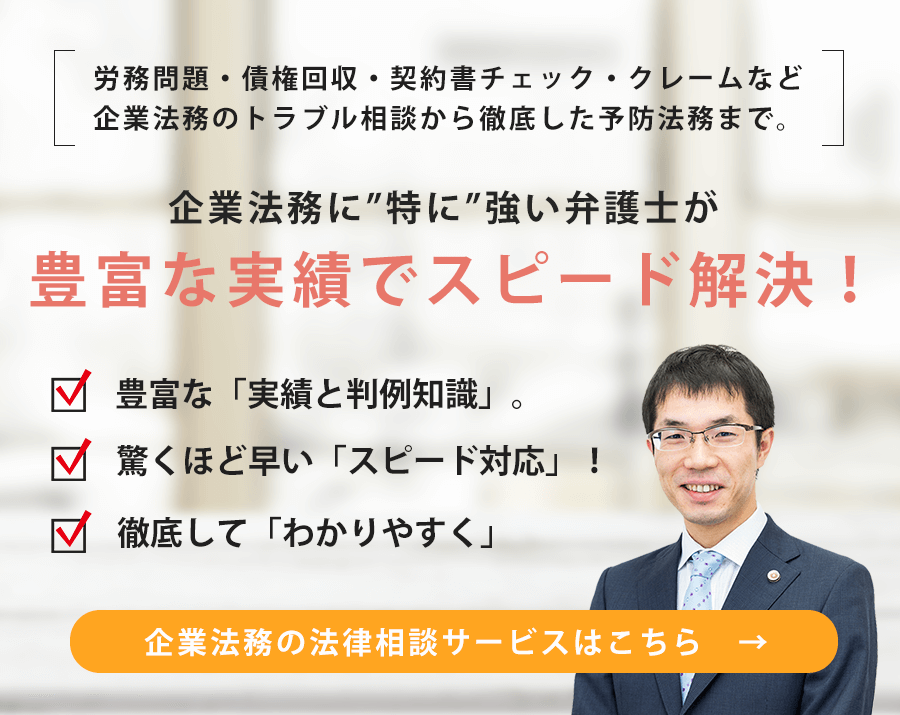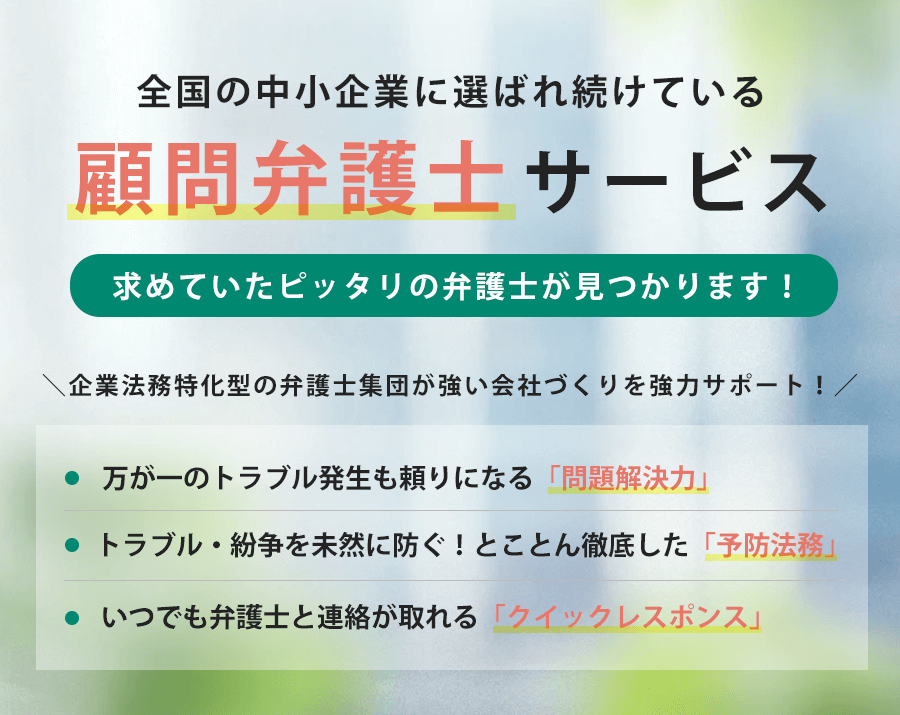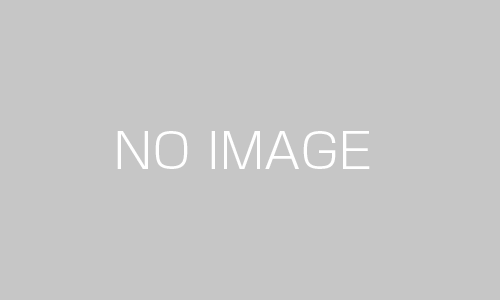最高裁H18.10.6
工場勤務の従業員が、課長代理に大声で怒鳴ったうえ、ネクタイや襟をつかんでその体を壁に押し付けるなどの暴行を加えた。 翌日も、課長代理を他の従業員とともに取り囲み、身動きできないようにして、膝を蹴り上げるなどの暴行を加え、課長代理が負傷
さらに、3か月後に、今度は、左手を課長代理の首に回し、右手で腹部をなぐる暴行。 会社は、課長代理が警察署などに告訴状を提出したことから、捜査の経過をまって会社としての処分を決めることした。 約6年後に検察官が不起訴処分を決めて通知。会社はこの従業員を諭旨退職処分としたが、この従業員が退職願を提出しなかったため、懲戒解雇。
→諭旨退職処分は事件から7年以上が経過した後にされたものであるところ、各事件は職場で就業時間中に管理職に対して行われた暴行事件であり、目撃者が存在したのであるから、捜査の結果を待たずとも処分を決めることは十分に可能であった。本件において長期間にわたって懲戒権の行使を留保する合理的な理由は見いだし難い。
しかも、使用者が従業員の非違行為について捜査の結果を待ってその処分を検討することとした場合において捜査の結果が不起訴処分となったときには、使用者においても懲戒解雇処分のような重い懲戒処分は行わないこととするのが通常の対応と考えられる。 本件各事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠く。諭旨退職処分、懲戒解雇処分ともに無効と判断。
この事例のように、刑事処分の結果が出るまで異常に長くかかることもあります。
起訴されたか、不起訴になったかということも、懲戒処分が重すぎないかという観点から懲戒処分の有効性にも影響するため、難しいところではありますが、社内での非違行為、私生活上の非違行為、どちらについても、刑事処分の結果を待たずに、会社において事情聴取を行い、必要な処分をすることを基本とすべきです。