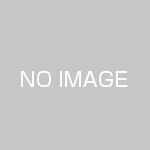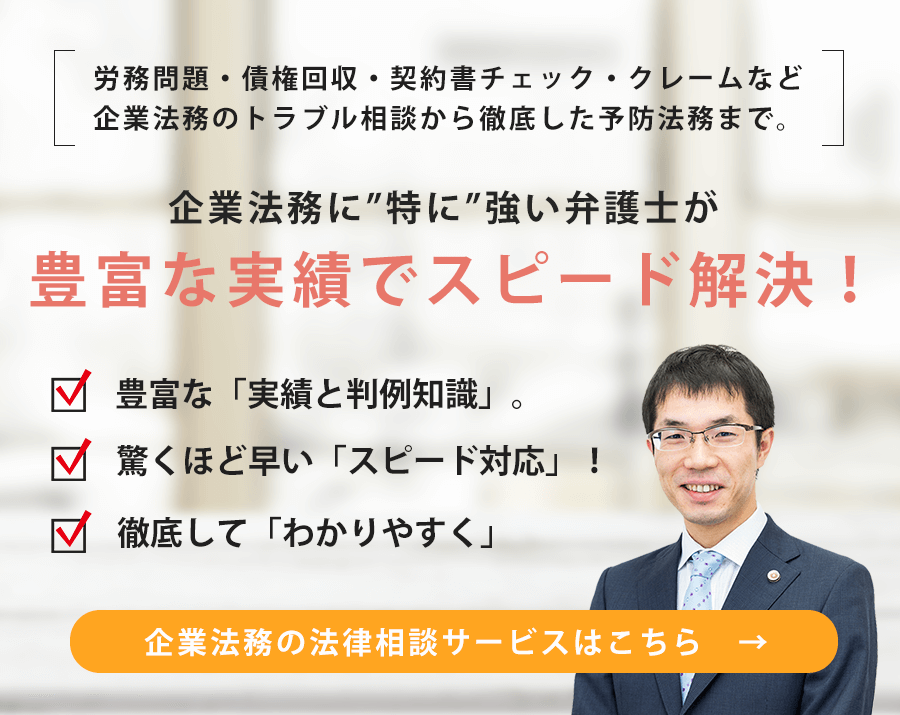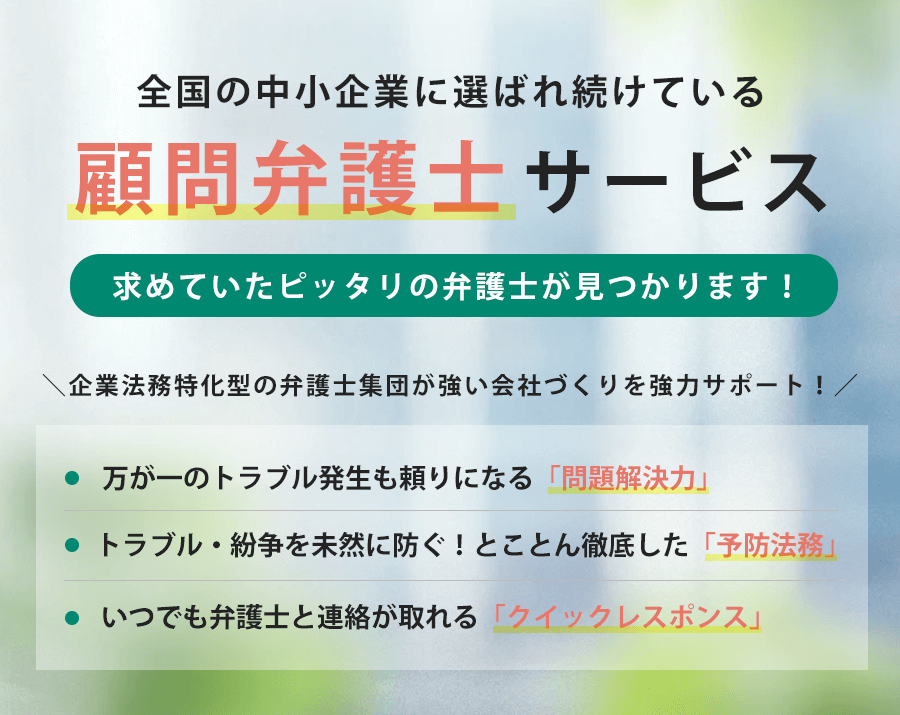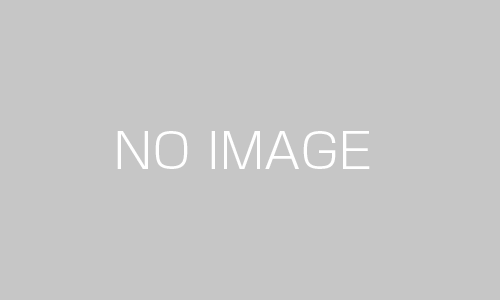東京地裁R6.5.13
会社は、住居の移転を伴う転勤に応じることができる従業員(総合職)についてのみ、会社が社宅を借り上げて賃料の約8割を会社が負担する社宅制度の利用を認め、一般職の従業員には認めず。一般職従業員はこれが違法な間接性差別であると主張。
→社宅の貸与について、性別以外の事由を要件とする措置であっても、他の性の構成員と比較して一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを合理的な理由なく講ずることは、違法とされるべき場合が想定される。この点、直近約10年間に在籍した総合職は男性29名、女性1名であるのに対し、一般職は男性1名、女性5名であった。また、会社による社宅制度の実際の運用は、総合職でありさえすれば、転勤の有無や現実的可能性のいかんを問わず、通勤圏内に自宅を所有しない限り希望すれば適用されるというのが実態であった。その恩恵を受けたのは、1名を除き全て男性であったということになる。措置の内容として、社宅制度を利用できる従業員とそうでない従業員の間で、経済的恩恵の格差はかなり大きい。他方で、転勤の事実やその現実的可能性の有無を問わず社宅制度の適用を認めている運用等に照らすと、会社が主張するような営業職のキャリアシステム上の必要性や、営業職の採用競争における優位性の確保という観点から、社宅制度の利用を総合職に限定する合理性を根拠づけることは困難。会社の社宅制度の運用は雇用分野における男女の均等な待遇を確保するという雇用機会均等法の趣旨に照らし、間接差別に該当する。違法と判断し、会社に約380万円の賠償命令。
参考:本件についての報道記事です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE135X80T10C24A5000000/
企業に潜む【意図しない男女差別】=間接差別リスクに要注意です。気づきにくいリスクと感じます。【これのなにがあかんの?】と思ってしまう人もいるように思いますが、男女雇用機会均等法、性差別禁止指針のルールの確認が必要です。
本件でも会社は男女差別の意図はなかったと感じますが、違法と判断されました。賠償額もさることながら、「間接差別」「男女差別」などと報道されると企業イメージへの悪影響、採用への悪影響が懸念されます。 ルール自体も難しく、労務のプロによる目配りが大切と感じます。就業規則の規定についても、募集、採用、労働者の配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種や雇用形態の変更、定年、解雇、労働契約の更新等に関して、形式的には性別と無関係の規定であっても、合理的な理由がなく実質的にみて一方の性の従業員に不利益が生じさせる内容になっていないか、確認しておくことが必要です。