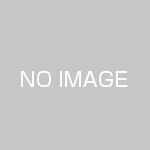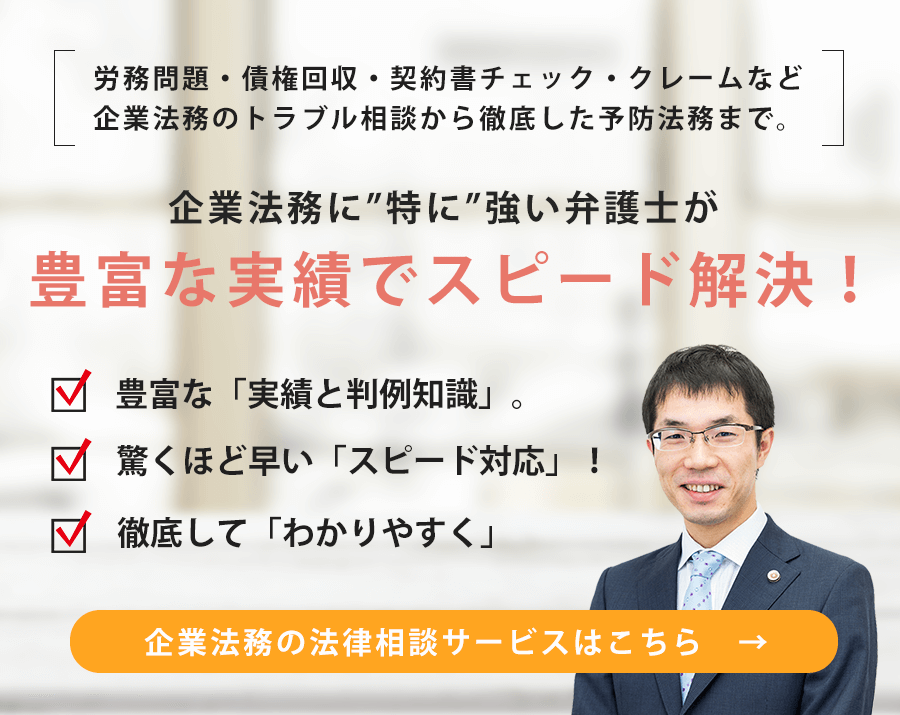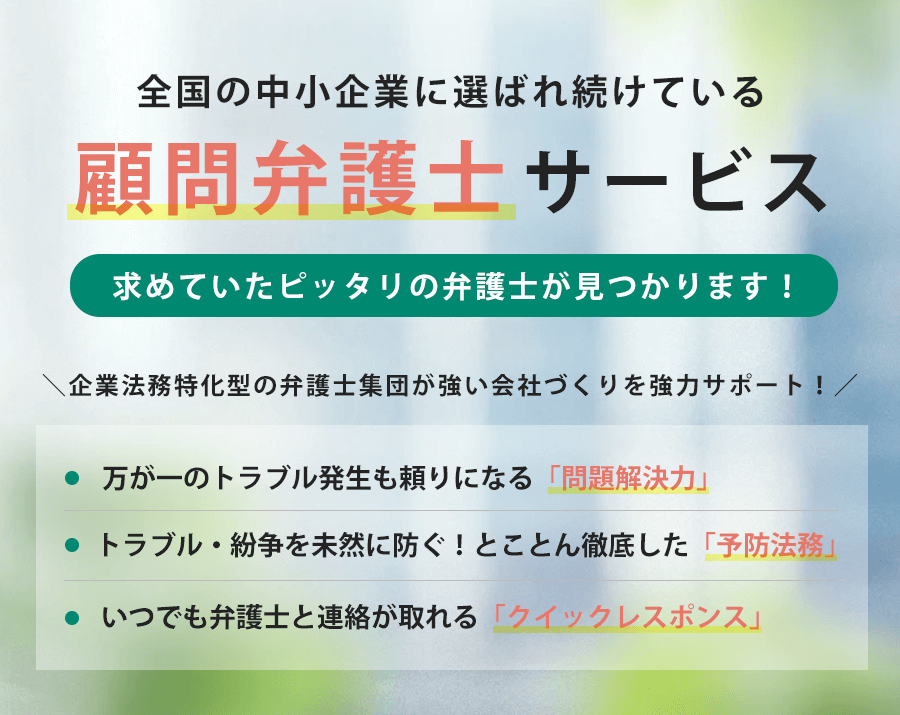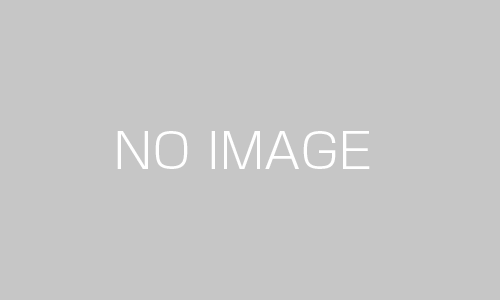鳥取地裁R7.1.21
ガソリンスタンドなどの事業を営む会社で、男性職員が勤務中の女性職員を無断で撮影。これに気付いた女性職員が悩んで上司に相談したが解消されず、翌月心身症と診断され、休職に至った
→会社がハラスメントを許容しない旨を従業員に周知し、ハラスメント相談を受けた場合は事実関係を確認し、再発防止策を講じるなどと従業員に周知していたことなどからすれば、女性職員に深刻な精神的苦痛が生じている可能性が極めて高い状況を認識したのだから、会社には速やかに事実関係を確認し、配置換えをするなど、女性職員に対する適切な配慮をしていく義務があった。
この点、本件で、会社は配置換えについて検討したり、顧客対応以外のスマートフォンの利用を控えるよう従業員に周知したり、ハラスメント行為に対する注意喚起のポスターを掲示したりしており、全く対応をしなかったわけではない。しかし、女性職員に対する詳細な事情聴取はおろか、男性職員に対する速やかな事情聴取さえ行わず、事件から約10か月経過した頃になってはじめて男性職員に事情聴取をした。その後も、女性職員に対して他のサービススタンドへの配置換えを打診した程度で特段の配慮ある行動をとっていない。しかも、会社は、服を着た姿を撮影されたもので盗撮事件とまではいえないとか、男性職員が退職するような事態とならないように慎重に対応しようとしたなどという認識の下で対応をしており、このような認識は、心身症と診断され休職するに至ったという被害結果を適切に評価しておらず、また、被害者と加害者の優先順位を見誤った不適切なものといわざるを得ない。以上によれば、会社は、不適切な認識の下、従業員に対してかねてから周知していた方針に反し、事実関係の確認をせず、女性職員に対する適切な配慮もしなかったもので、労働契約上の付随義務に違反したというべきである。この義務違反について会社に対し44万円の賠償命令。