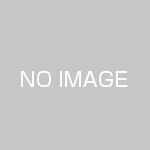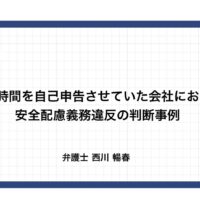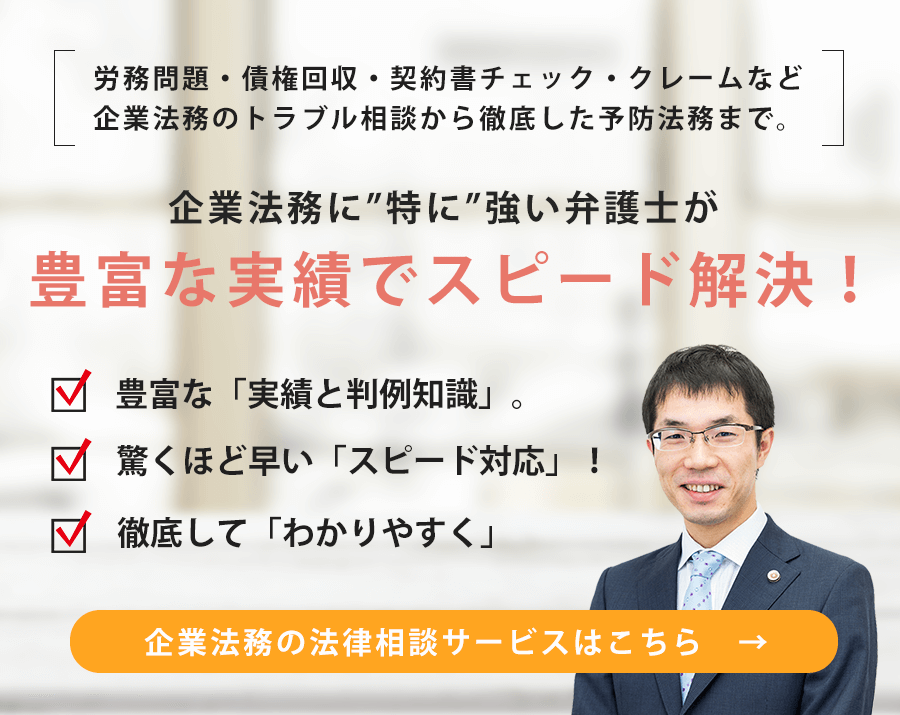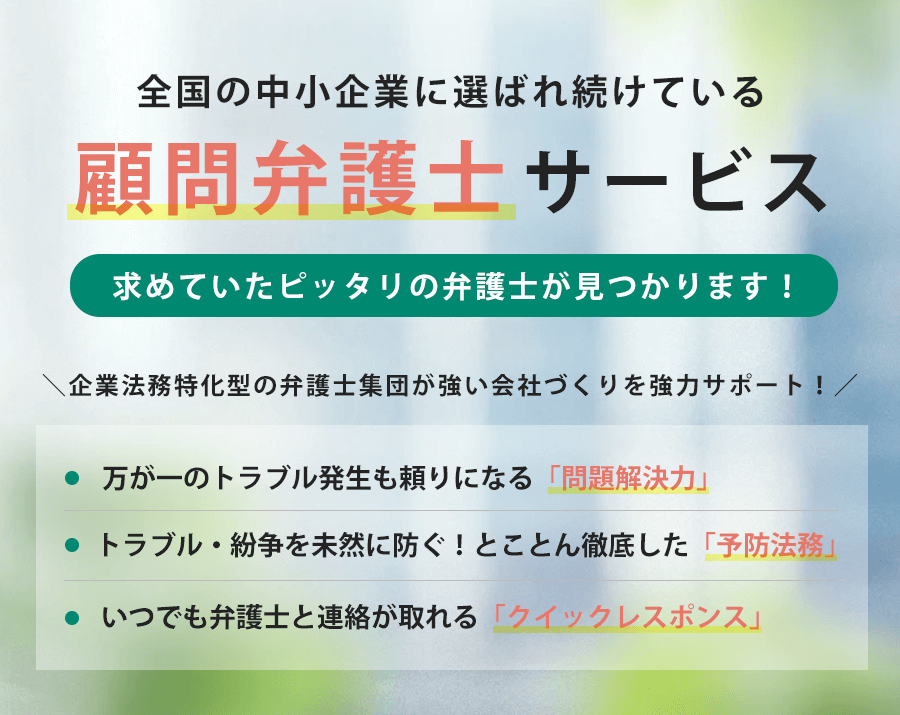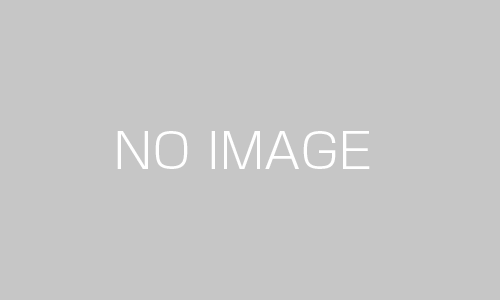大阪高裁R7.10.14
私立高校に有期雇用されていた講師が、仕事内容が同じなのに、無期雇用の教員よりも基本給(年齢給)が低いのは違法であると主張
→本件高校の無期雇用の教員の年齢給は、長期雇用を前提に、基幹的な地位・役割を担うことが期待される人材の確保などの目的から定められたもので、基本的職務の遂行に対する職務給に、長期勤続による能力向上等に応じた勤続給等の要素が加えられた複合的な性質がある。これに対し、有期雇用の講師の年齢給は、本来的には短期雇用であることを前提に、教職員としての基本的な職務遂行に対する職務給を中心とするものであり、無期雇用の教員の年齢給とは目的及び性質が異なる。
また、無期雇用の教員と有期雇用の講師の間に、職務内容に大きな差異はないが、管理職ないし役職には例外的な場面を除き無期雇用教員が就任し、無期雇用教員は系列校への異動があるなど、人事異動の範囲には大きな差異がある。
そして、有期雇用の講師も試験を受けて合格すれば無期雇用の教員になることができ、その際に一定の優遇措置が設けられている。 これらの点を踏まえると、本件高校において、無期雇用の教員と有期雇用の講師の賃金額に差を設けることには一定の合理性がある。年齢給の差が3割以内にとどまり、年齢給以外の賃金については、講師であっても無期雇用教員と同様に期末手当その他の諸手当の支給がされることを考慮すれば、本件の年齢給の差が不合理なものに至っているとまではいえない。違法ではないと判断
本件の報道です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG2949Y0Z21C25A0000000/
大阪高裁で結論逆転。格差の違法を訴えた労働者が敗訴しました。
一審は格差違法としていましたが、控訴審は適法と結論を変更しました。控訴審では、本件の有期雇用の講師の年齢給は、無期雇用の教員の年齢給とは目的及び性質が異なるとしています。目的及び性質が異なるのであれば両者を比べようがなくどこまで格差があっても違法とはされないという考えもありそうですが、控訴審判決はそうではなく、目的及び性質が異なっても、格差が大きすぎれば違法になりうるという考えをとったうえで、本件で問題になった格差(3割以内)は適法の範囲内としました。
ただし、この高校の賃金制度は勤続を重ねるにつれて格差が広がる内容なので、控訴審判決の論理で行けば、このまま放置すればどこかで違法になると思われ、法人としては賃金制度の見直しが必要になります。
ただし、本判決は上告されており、最高裁の判断が注目されます。 先月出たばかりなのでまだ判例集には掲載されていませんが、雑誌【労働判例】に掲載される予定です。